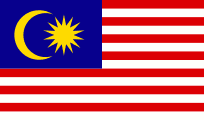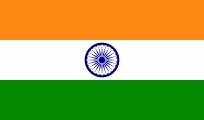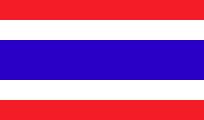ψ¹™ψ²™ψ¹Ϊψ¹Γψ¹·ψĹψÉôψÉàψÉäψɆψĹψÉèψÉéψ²Λφî·ιÉ®ψ¹°εΑèγħψ¹ßψ¹ôψIJ
δΦ¹φΞ≠ψ²³εÄ΄δΚΚψ¹°φ¥Με΄ïψ¹¨ψ²ΑψÉ≠ψÉΦψÉêψÉΪ娕ψ¹ôψ²΄γèΨδΜΘψ¹Ϊψ¹äψ¹³ψ¹ΠψĹε¦ΫεΔÉψ²£ηΕäψ¹àψ¹üγßüγ®éε¦ûι¹Ωψ¹·ψĹεê³ε¦Ϋψ¹°γ®éψ¹°εÖ§εΙ≥φÄßψ²£ηë½ψ¹½ψ¹èφêçψ¹Σψ¹ÜεïèιΓ¨ψ¹ßψ¹ôψIJψ¹™ψ¹°εïèιΓ¨ψ¹Ϊε·Ψε΅Πψ¹ôψ²΄ψ¹üψ²¹ψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹ßψ¹·2019εΙ¥γ®éε΄ôγ°ΓγêÜφ≥ïψ¹¨φ•ΫηΓ¨ψ¹ïψ²¨ψ¹Ψψ¹½ψ¹üψIJφ€§φ≥ïψ¹°δΗ≠ψ¹ßψ²²ψĹγâΙψ¹Ϊ㧧12φùΓψĨγ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹Ϊψ²àψ²΄ε¦Ϋιö¦εçîεä¦ψÄçψ¹·ψĹεÖ§εΙ≥ψ¹Σγ®éη≤†φ΄Öψ²£ε°üγèΨψ¹ôψ²΄ψ¹üψ²¹ψ¹°ιùûεΗΗψ¹Ϊι΅çηΠ¹ψ¹ΣψÉΪψÉΦψÉΪψ²£ε°öψ²¹ψ¹Πψ¹³ψ¹Ψψ¹ôψIJ
γ®éε΄ôγ°ΓγêÜφ≥ï㧧12φùΓψ¹Ϊε°öψ²¹ψ²âψ²¨ψ¹üγ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹°δΗΜψ¹Ση≤§ε΄ô
φ€§φùΓψ¹Ϊψ¹äψ¹³ψ¹ΠψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹°γ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹·δΜΞδΗ΄ψ¹°η≤§ε΄ôψ²£η≤†ψ¹Üψ¹™ψ¹®ψ¹¨φ‰éγΔΚψ¹ΪηΠèε°öψ¹ïψ²¨ψ¹Πψ¹³ψ¹Ψψ¹ôψIJ
- ε¦Ϋιö¦φùΓγ¥³ψ¹°δΚΛφΗâψÉΜγΖ†γΒêφî·φè¥οΦö ψÉôψÉàψÉäψɆψ¹¨γΖ†γΒêψ¹ôψ²΄ε¦Ϋιö¦φùΓγ¥³οΦàγßüγ®éφùΓγ¥³γ≠âοΦâψ¹Ϊι•Δψ¹½ψĹδΚΛφΗâψ¹°φèêφΓàψĹγΫ≤εêçψĹφ®©εà©γΨ©ε΄ôψ¹°ηΓ¨δΫΩψ¹Ϊψ¹Λψ¹³ψ¹Πη≤Γε΄ôεΛßη΅Θψ¹Ϊεä©η®Äψ¹½ψĹε¦Ϋγ¦äψ²£γΔΚδΩùψ¹ôψ²΄ψIJ
- δΚ¨ε¦Ϋι•™ψÉΜεΛöε¦Ϋι•™εçîε°öψ¹°ε°üφ•ΫοΦö εΛ•ε¦Ϋψ¹°γ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹®ψ¹°ι•™ψ¹ßψĹγ®éψ¹Ϊι•Δψ¹ôψ²΄δΚ¨ε¦Ϋι•™ψ¹Ψψ¹üψ¹·εΛöε¦Ϋι•™ψ¹°εçîε°öψ²£δΚΛφΗâψÉΜγΖ†γΒêψ¹½ψĹψ¹ùψ¹°ε°üφ•Ϋψ²£δΗΜεΑéψ¹ôψ²΄ψIJ
- φÉÖ冱δΚΛφè¦ψ¹®εΑ²ι•Äγö³εçîεä¦οΦö εΛ•ε¦Ϋψ¹°γ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ²³ε¦Ϋιö¦φ©üι•Δψ¹®ιÄΘφêΚψ¹½ψĹφÉÖ冱δΚΛφè¦ψ²³εΑ²ι•Äγö³ψ¹Σεçîεä¦ψ²£φé®ιÄ≤ψ¹ôψ²΄ψIJγâΙψ¹Ϊι•ΔιÄΘηÄÖι•™εè•εΦïοΦàγßΜηΜΔδΨΓφ†Φγ®éεàΕοΦâψ¹°γ°ΓγêÜψ²£γ¦°γö³ψ¹®ψ¹½ψ¹ΠψĹγ¥çγ®éηÄÖψ¹äψ²àψ¹≥ψ¹ùψ¹°ε¦ΫεΛ•ι•ΔιÄΘηÄÖψ¹Ϊι•Δψ¹ôψ²΄φÉÖ冱ψ²£δΚΛφè¦ψ¹ôψ²΄ψIJ
- εΨ¥γ®éεçîεä¦οΦàεΨ¥εèéεÖ±εä©οΦâψ¹°ε°üφ•ΫοΦö ψÉôψÉàψÉäψɆψ¹¨γΖ†γΒêψ¹½ψ¹üε¦Ϋιö¦φùΓγ¥³ψ¹ΪεüΚψ¹Ξψ¹çψĹδΜΞδΗ΄ψ²£εêΪψ²ÄεΨ¥γ®éφî·φè¥φéΣγΫ°ψ²£ε°üφ•Ϋψ¹ôψ²΄ψIJ
- (a) ε¦ΫεΛ•ψ¹ßψ¹°ψÉôψÉàψÉäψɆγ®éψ¹°εΨ¥εèéηΠ¹ηΪ΄οΦö γ¥çγ®éηÄÖψ¹¨ψÉôψÉàψÉäψɆψ¹΄ψ²âε΅Κε¦ΫψÉΜφ£ΛιÄÄψ¹½ψ¹ü冥εêàψĹγ¦Ηφâ΄ε¦Ϋψ¹°γ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹Ϊε·Ψψ¹½ψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹°φ€Σγ¥çγ®éι΅ëψ¹°εΨ¥εèéψ²£φî·φè¥ψ¹ôψ²΄ψ²àψ¹ÜηΠ¹ηΪ΄ψ¹ôψ²΄ψIJ
- (b) ε¦ΫεÜÖψ¹ßψ¹°εΛ•ε¦Ϋγ®éψ¹°εΨ¥εèéφî·φè¥οΦö εΛ•ε¦Ϋψ¹°γ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹΄ψ²âψ¹°ηΠ¹ηΪ΄ψ¹ΪεüΚψ¹Ξψ¹çψĹψÉôψÉàψÉäψɆε¦ΫεÜÖψ¹Ϊψ¹äψ¹ëψ²΄εΛ•ε¦Ϋψ¹°φ€Σγ¥çγ®éι΅ëψ¹°εΨ¥εèéψ²£φî·φè¥ψ¹ôψ²΄ψIJ
φ€Äι΅çηΠ¹ψÉùψ²ΛψÉ≥ψÉàοΦöε¦ΫεΛ•ψ¹ßψ¹°φ€Σγ¥çγ®éι΅ëψ¹Ϊε·Ψψ¹ôψ²΄εΨ¥εèéφ®©οΦà㧧12φùΓ4ι†ÖaεèΖοΦâ
δΗä箉ψ¹°δΗ≠ψ¹ßψ²²ψĹφ½Ξγ≥ΜδΦ¹φΞ≠ψ¹Ϊψ¹®ψ¹Θψ¹ΠγâΙψ¹Ϊι΅çηΠ¹ψ¹Σψ¹°ψ¹¨ψĨ(a) ε¦ΫεΛ•ψ¹ßψ¹°ψÉôψÉàψÉäψɆγ®éψ¹°εΨ¥εèéηΠ¹ηΪ΄ψÄçψ¹ßψ¹ôψIJψ¹™ψ²¨ψ¹·ψĹψ¹³ψ²èψ²Üψ²΄ψĨεΨ¥εèéεÖ±εä©ψÄçψ¹®εëΦψ¹Αψ²¨ψ²΄εàΕεΚΠψ¹ßψ¹²ψ²äψĹε°üε΄ôδΗäψĹφΞΒψ²¹ψ¹ΠεΦΖεä¦ψ¹ΣεΫ±ιüΩεä¦ψ²£φ¨¹ψ¹Γψ¹Ψψ¹ôψIJ
ψÄêεÖΖδΫ™γö³ψ¹Σψ²ΖψÉäψÉΣψ²ΣδΨ΄ψÄë
- φ½Ξφ€§ψ¹°AγΛΨψ¹¨ψÉôψÉàψÉäψɆψ¹ßεΖΞ冥ψ²£ι¹΄ε•Εψ¹½ψ¹Πψ¹³ψ¹Ψψ¹½ψ¹üψ¹¨ψĹφΞ≠γΗΨδΗçφ¨·ψ¹Ϊψ²àψ²äεΖΞ冥ψ²£ι•âιé•ψ¹½ψĹφ½Ξφ€§ψ¹Ηε°¨εÖ®φ£ΛιÄÄψ¹½ψ¹Ψψ¹½ψ¹üψIJ
- ψ¹ùψ¹°ιö¦ψĹ1,000δΗ΅εÜÜγ¦ΗεΫ™ψ¹°φ≥ïδΚΚγ®éψ²£ψÉôψÉàψÉäψɆγ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹Ϊφ€Σγ¥çψ¹°ψ¹Ψψ¹Ψε΅Κε¦Ϋψ¹½ψ¹Ψψ¹½ψ¹üψIJ
- ψÉôψÉàψÉäψɆγ®éε΄ôεΫ™ε±Äψ¹·ψĹψ¹™ψ¹°γ®éε΄ôγ°ΓγêÜφ≥ï㧧12φùΓψ¹äψ²àψ¹≥φ½ΞηΕäγßüγ®éφùΓγ¥³ψ¹ΪεüΚψ¹Ξψ¹çψĹφ½Ξφ€§ψ¹°ε¦Ϋγ®éεΚ¹ψ¹Ϊε·Ψψ¹½ψ¹ΠψĨAγΛΨψ¹΄ψ²â1,000δΗ΅εÜÜψ²£εΨ¥εèéψ¹½ψ¹Πψ¹èψ¹†ψ¹ïψ¹³ψÄçψ¹®εΨ¥εèéεÖ±εä©ψ²£ηΠ¹ηΪ΄ψ¹½ψ¹Ψψ¹ôψIJ
- ηΠ¹ηΪ΄ψ²£εè½ψ¹ëψ¹üφ½Ξφ€§ψ¹°ε¦Ϋγ®éεΚ¹ψ¹·ψĹφ½Ξφ€§ψ¹°φ≥ïεΨ΄ψ¹Ϊεâ΅ψ¹Θψ¹ΠAγΛΨψ¹΄ψ²âγ®éι΅ëψ²£εΨ¥εèéψ¹½ψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹Ϊγ¥çδΜ‰ψ¹ôψ²΄φâ΄γΕöψ¹çψ²£ηΓ¨ψ¹³ψ¹Ψψ¹ôψIJ
ψ¹™ψ²¨ψ¹Ϊψ²àψ²äψĹδΦ¹φΞ≠ψ¹·ψĨφ£ΛιÄÄψ¹½ψ¹Πψ¹½ψ¹Ψψ¹àψ¹ΑψĹγèΨε€Αψ¹ßψ¹°φ€Σφâïγ®éι΅ëψ¹·ι•ΔδΩ²ψ¹Σψ¹³ψÄçψ¹®ψ¹·ηÄÉψ¹àψ²âψ²¨ψ¹Σψ¹èψ¹Σψ²äψ¹Ψψ¹½ψ¹üψIJ
εΨ¥εèéεçîεä¦ψ¹°εâçφèêφùΓδΜΕοΦöψĨε¦Ϋιö¦φùΓγ¥³ψÄçψ¹°ε≠‰ε€®
ψ¹üψ¹†ψ¹½ψĹψ¹™ψ¹°εΦΖεä¦ψ¹ΣφéΣγΫ°ψ¹·ψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹¨δΗÄφ•Ιγö³ψ¹Ϊψ¹©ψ¹°ε¦Ϋψ¹Ϊε·Ψψ¹½ψ¹Πψ²²ηΓ¨δΫΩψ¹ßψ¹çψ²΄ψ²èψ¹ëψ¹ßψ¹·ψ¹²ψ²äψ¹Ψψ¹¦ψ²™ψIJεΩÖψ¹öψĹδΗΓε¦Ϋι•™ψ¹ßψĨε¦Ϋιö¦φùΓγ¥³ψÄçψĹεÖΖδΫ™γö³ψ¹Ϊψ¹·γßüγ®éφùΓγ¥³ψ¹Ϊψ¹äψ¹ëψ²΄ψĨεΨ¥εèéεÖ±εä©ψÄçψ¹°ηΠèε°öψ¹¨γΒêψ¹Αψ²¨ψ¹Πψ¹³ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ¹¨εâçφèêψ¹®ψ¹Σψ²äψ¹Ψψ¹ôψIJ
εΙΗψ¹³ψ¹Ϊψ²²ψĹφ½Ξφ€§ψ¹®ψÉôψÉàψÉäψɆψ¹°ι•™ψ¹ßψ¹·ψĹψ¹™ψ¹°εΨ¥εèéεÖ±εä©ψ²£εêΪψ²Äγßüγ®éφùΓγ¥³ψ¹¨φ€âεäΙψ¹ΪγΖ†γΒêψ¹ïψ²¨ψ¹Πψ¹³ψ¹Ψψ¹ôψIJ
γΒêηΪ•ψ¹®ψ¹½ψ¹ΠψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹΄ψ²âφ£ΛιÄÄψ¹½ψ¹üεΨ¨ψ¹ßψ¹²ψ¹Θψ¹Πψ²²ψĹφ€Σγ¥çγ®éι΅ëψ¹¨ψ¹²ψ²¨ψ¹Αφ½Ξφ€§ψ¹°ε¦Ϋγ®éεΚ¹ψ²£ιÄöψ¹‰ψ¹ΠεΦΖεàΕγö³ψ¹ΪεΨ¥εèéψ¹ïψ²¨ψ²΄εè·ηÉΫφÄßψ¹¨ψ¹²ψ²äψ¹Ψψ¹ôψIJ ψ¹™ψ¹°δΚ΄ε°üψ¹·ψĹψÉôψÉàψÉäψɆψ¹ßδΚ΄φΞ≠ψ²£ηΓ¨ψ¹Üψ¹ôψ¹Ιψ¹Πψ¹°δΦ¹φΞ≠ψ¹Ϊψ¹®ψ¹Θψ¹ΠψĹφ½ΞψÄÖψ¹°φ≠ΘγΔΚψ¹Σγ®éε΄ôψ²≥ψÉ≥ψɽψÉ©ψ²Λψ²ΔψÉ≥ψ²Ιψ¹¨ψ¹™ψ²¨ψ¹Ψψ¹ßδΜΞδΗäψ¹Ϊι΅çηΠ¹ψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ²£γΛΚεîÜψ¹½ψ¹Πψ¹³ψ¹Ψψ¹ôψIJ
δΫïψ¹΄η≥Σεïèγ≠âψ¹îψ¹•ψ¹³ψ¹Ψψ¹½ψ¹üψ²âψĹψ¹îη≥Σεïèψ¹³ψ¹üψ¹†ψ¹ëψ¹Ψψ¹ôψ¹®εΙΗψ¹³ψ¹ßψ¹ôψIJ