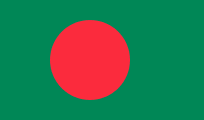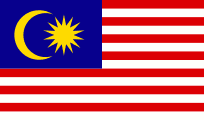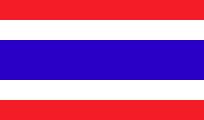гғҷгғҲгғҠгғ гғ»гғҸгғҺгӮӨж”ҜйғЁгҒ®е°ҸзҖ¬гҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬ж—ҘгҒҜгҖҒжңҲжң«гҒ«йҖҖиҒ·гҒ•гӮҢгӮӢеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®зӨҫдјҡдҝқйҷәжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒе®ҹеӢҷдёҠиҰӢиҗҪгҒЁгҒ•гӮҢгҒҢгҒЎгҒӘгҖҢжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®гӮҝгӮӨгғ гғ©гӮ°гҖҚгҒ«иө·еӣ гҒҷгӮӢе•ҸйЎҢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘи§Јжұәзӯ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжң¬д»¶гҒҜгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒЁдјҒжҘӯеҸҢж–№гҒ®дәҲжңҹгҒӣгҒ¬дёҚеҲ©зӣҠгӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒдәәдәӢйғЁй–ҖгҒ®жҘӯеӢҷеҠ№зҺҮгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
1. гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«пјҡе®ҹеӢҷдёҠж•ЈиҰӢгҒ•гӮҢгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚйҒ…延гҒ®дәӢдҫӢ
гғҷгғҲгғҠгғ гҒ®дәәдәӢгҒ”жӢ…еҪ“иҖ…ж§ҳгҒҜгҖҒжңҲжң«йҖҖиҒ·иҖ…гҒ®зӨҫдјҡдҝқйҷәжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иҝ…йҖҹгҒ«йҖІгӮҒгҒҹгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒеҫҢж—ҘгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгӮ„зӨҫдјҡдҝқйҷәдәӢеӢҷжүҖгҒӢгӮүе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҒ”зөҢйЁ“гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
е…ёеһӢзҡ„гҒӘдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ9жңҲжң«йҖҖиҒ·гҒ®еҫ“жҘӯе“ЎгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ10жңҲдёҠж—¬гҒ«гҖҢиіҮж је–ӘеӨұеұҠгҖҚгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҒҹгӮұгғјгӮ№гӮ’жғіе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдәәдәӢйғЁй–ҖгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒ§жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜе®ҢдәҶгҒ—гҒҹгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—еҫҢж—ҘгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒӢгӮүгҖҢж–°дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒёгҒ®еҠ е…ҘгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁйҖЈзөЎгҒҢе…ҘгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒзӨҫдјҡдҝқйҷәдәӢеӢҷжүҖгҒӢгӮүгҒҜгҖҢжңҖзөӮдҝқйҷәж–ҷгҒҢжңӘзҙҚгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒиіҮж је–ӘеӨұеҮҰзҗҶгҒҢе®ҢдәҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ®з…§дјҡгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶдәӢж…ӢгҒҢзҷәз”ҹгҒ—еҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®йҒҺиӘӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҲ¶еәҰйҒӢз”ЁдёҠгҒ®гҖҢгӮҝгӮӨгғ гғ©гӮ°гҖҚгҒҢеј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷж§ӢйҖ зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
2. е•ҸйЎҢгҒ®ж§ӢйҖ еҲҶжһҗпјҡгҒӘгҒңж„ҸеӣігҒӣгҒ¬гҖҢдҝқз•ҷгҖҚзҠ¶ж…ӢгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢ
гҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгҒ®ж ёеҝғгҒҜгҖҒгҖҢиіҮж је–ӘеӨұеұҠгҒ®жҸҗеҮәгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҖҚгҒЁгҖҢзӨҫдјҡдҝқйҷәж–ҷгҒ®жңҖзөӮзҙҚд»ҳгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҖҚгҒЁгҒ®й–“гҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰдёҠгҒ®гӮ®гғЈгғғгғ—гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- дјҒжҘӯеҒҙгҒ®е®ҹеӢҷгғ—гғӯгӮ»гӮ№ иіҮж је–ӘеӨұеұҠгҒҜйҖҖиҒ·еҫҢйҖҹгӮ„гҒӢгҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҜҫиұЎеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®жңҖзөӮжңҲеҲҶпјҲдҫӢпјҡ9жңҲеҲҶпјүгҒ®дҝқйҷәж–ҷгҒҜгҖҒиҰҸзЁӢйҖҡгӮҠзҝҢжңҲжң«пјҲ10жңҲжң«пјүгҒ«д»–гҒ®еңЁзұҚеҫ“жҘӯе“ЎеҲҶгҒЁеҗҲз®—гҒ—гҒҰзҙҚд»ҳгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
- зӨҫдјҡдҝқйҷәдәӢеӢҷжүҖгҒ®еҜ©жҹ»еҹәжә– дәӢеӢҷжүҖеҒҙгҒҜгҖҒгҖҢиіҮж је–ӘеӨұеұҠгҖҚгӮ’еҸ—зҗҶгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҜҫиұЎжңҲгҒ®дҝқйҷәж–ҷзҙҚд»ҳгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§иіҮж је–ӘеӨұжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®еҜ©жҹ»еҹәжә–гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдјҒжҘӯгҒҢ10жңҲдёҠж—¬гҒ«еұҠеҮәгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒ10жңҲжң«гҒ«дҝқйҷәж–ҷгҒҢзҙҚд»ҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§зҙ„3йҖұй–“гҒ®гҖҢдҝқз•ҷгҖҚжңҹй–“гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ®зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
3. жүӢз¶ҡгҒҚеҒңж»һгҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒҷжҪңеңЁзҡ„гғӘгӮ№гӮҜ
гҒ“гҒ®гҖҢдҝқз•ҷгҖҚзҠ¶ж…ӢгҒҜгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒЁдјҒжҘӯгҒ®еҸҢж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒзңӢйҒҺгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еҶ…еҢ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- гғӘгӮ№гӮҜв‘ пјҡе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®ж–°еҲ¶еәҰгҒёгҒ®з§»иЎҢйҒ…延 е…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒҢеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгӮ„и»ўиҒ·е…ҲгҒ®еҒҘеә·дҝқйҷәзө„еҗҲгҒёеҠ е…ҘгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒгҖҢеүҚиҒ·гҒ®иіҮж јгҒҢе–ӘеӨұгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶз”ұгҒ«жүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҒңж»һгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠж–°дҝқйҷәиЁјгҒ®зҷәиЎҢгҒҢйҒ…延гҒ—гҖҒжңҹй–“еҶ…гҒ«еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮ’еҸ—иЁәгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҢ»зҷӮиІ»гҒ®дёҖжҷӮзҡ„гҒӘе…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…гӮ’еј·гҒ„гӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
- гғӘгӮ№гӮҜв‘ЎпјҡдјҒжҘӯпјҲдәәдәӢйғЁй–ҖпјүгҒёгҒ®жҘӯеӢҷеҪұйҹҝ е®ҢдәҶгҒ—гҒҹгҒЁиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«й–ўгҒ—гҖҒзӨҫдјҡдҝқйҷәдәӢеӢҷжүҖгҒӢгӮүгҒ®з…§дјҡгӮ„е…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒӢгӮүгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣеҜҫеҝңгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҺҹеӣ иӘҝжҹ»гӮ„еҶҚжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйқһеҠ№зҺҮгҒӘдәӢеӢҷзҡ„жүӢжҲ»гӮҠгҒҢз”ҹгҒҳгҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬з®ЎзҗҶгӮігӮ№гғҲгҒҢеў—еӨ§гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
4. жңҖгӮӮзўәе®ҹгҒӘгғӘгӮ№гӮҜеӣһйҒҝзӯ–пјҡжңҖзөӮдҝқйҷәж–ҷгҒ®гҖҢеҪ“жңҲзҙҚд»ҳгҖҚ
дёҠиЁҳгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жңҖгӮӮзўәе®ҹгҒӢгҒӨеҗҲзҗҶзҡ„гҒӘи§Јжұәзӯ–гҒҜгҖҒжңҖзөӮдҝқйҷәж–ҷгҒ®зҙҚд»ҳгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’еүҚеҖ’гҒ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮўгӮҜгӮ·гғ§гғігғ—гғ©гғігҖ‘ жңҲжң«йҖҖиҒ·иҖ…гҒ®жңҖзөӮжңҲеҲҶзӨҫдјҡдҝқйҷәж–ҷгӮ’гҖҒжң¬жқҘгҒ®зҙҚд»ҳжңҹйҷҗпјҲзҝҢжңҲжң«пјүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйҖҖиҒ·еҪ“жңҲдёӯгҒ«зҙҚд»ҳеҮҰзҗҶгӮ’е®ҢдәҶгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒӘжҺӘзҪ®гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзӨҫдјҡдҝқйҷәдәӢеӢҷжүҖгҒҢиіҮж је–ӘеӨұеұҠгӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ«гҒҜгҖҒж—ўгҒ«жңҖзөӮжңҲгҒ®дҝқйҷәж–ҷгҒҢзҙҚд»ҳжёҲгҒҝгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢгҖҢдҝқз•ҷгҖҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒйҒ…ж»һгҒӘгҒҸе®ҢдәҶгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
5. зөҗи«–
жңҲжң«йҖҖиҒ·иҖ…гҒ®зӨҫдјҡдҝқйҷәжүӢз¶ҡгҒҚгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮҝгӮӨгғ гғ©гӮ°гҒҜгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒ®еҶҶж»‘гҒӘ移иЎҢгӮ’еҰЁгҒ’гҖҒдјҒжҘӯгҒ®з®ЎзҗҶгӮігӮ№гғҲгӮ’еў—еӨ§гҒ•гҒӣгӮӢиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖзөӮдҝқйҷәж–ҷгҒ®гҖҢеҪ“жңҲзҙҚд»ҳгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёҖжӯ©йҖІгӮ“гҒ еҜҫеҝңгҒҜгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдјҒжҘӯгҒ®иӘ е®ҹгҒӘй…Қж…®гӮ’зӨәгҒҷгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒиҮӘзӨҫгҒ®дәӢеӢҷеҮҰзҗҶгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒ—гҖҒгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҗдёҠгҒ§жҘөгӮҒгҒҰжңүеҠ№гҒӘжүӢжі•гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖзөӮдҝқйҷәж–ҷгҒ®гҖҢеҪ“жңҲзҙҚд»ҳгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғӯгӮўгӮҜгғҶгӮЈгғ–гҒӘеҜҫеҝңгҒҜгҖҒе…ғеҫ“жҘӯе“ЎгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӘ е®ҹгҒӘй…Қж…®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒиҮӘзӨҫгҒ®дәӢеӢҷеҮҰзҗҶгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒҷгӮӢдёҠгҒ§гӮӮжҘөгӮҒгҒҰжңүеҠ№гҒӘжүӢжі•гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒңгҒІгҖҒиІҙзӨҫгҒ®йҒӢз”Ёгғ•гғӯгғјиҰӢзӣҙгҒ—гҒ®гҒ”еҸӮиҖғгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҒЁе№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
дҪ•гҒӢиіӘе•ҸзӯүгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒ”иіӘе•ҸгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒҷгҒЁе№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ